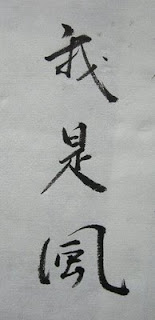シュリナガラ2日目

シュリナガル二日目。 町を案内してもらい、いくつか庭園に連れて行ってもらいました。 どこを見ても驚きです。 お金を求めに来る人もすべてが僕にとって新鮮であり衝撃的でした。 100円でも差し上げたら喜ぶだろうなと思いながらも一銭も出しませんでした。明らかに僕達日本人とは、行い、ものの考え方、生活レベルが全然違うのだろうけど、僕はいつも同じ魂を持っている兄弟である事は常に意識し続けた。 どうあがいても現在の生活から抜け出せない人間がいるのは確かだ。それを“強い信仰”というもの支えているのかもしれないと考えたりした。 なんやら分かっている気になって書いているが、所詮上から目線なのはわかっているつもりだ。 明日はいよいよヒマラヤ山脈へ!!
.JPG)